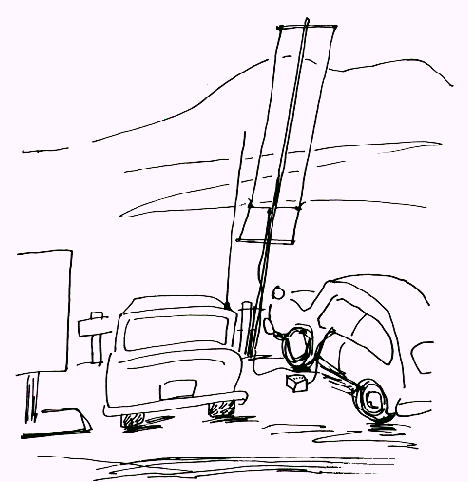
| ・戻 る | ホーム | 進む・ |
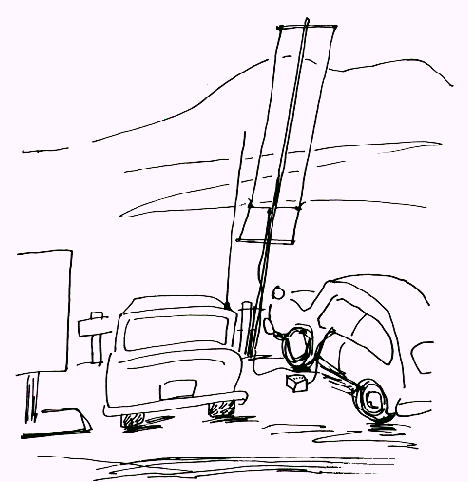
「ヘンテナ」という妙な名前のついたアンテナをあなたは知っていますか。
名前こそふざけていますが、このページをお読みいただくことによってあなたもヘンテナのファンになること間違いなしです。 丁度私がヘンテナのとりこに
なってしまったように…。
「ヘンテナ」の語源は、多分あなたが考えるであろうと思われる通り「変な動作をするアンテナ」から付けられています。
ヘンテナに関するいろいろの話は追い追いお話するとして、まずその基本的な形を知っておいてください。
1-1図をごらんください。まず幅1/6λ、長さ1/2λのループを作ります。 そして、そのループに1-2図に示すように50Ωのケー
ブルで給電します。
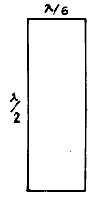 |
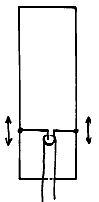 |
|
|
|
SWRの調整は1-2図に示すようにループに対する給電位置を上下させます。
出来れば給電点にバランを入れてバランスを取ってください。
これで水平偏波のヘンテナの出来上がりです。
「エッ!水平偏波ですか?」と驚く方が出てくるかも知れませんね。 そうです。 まずこれが「第1の変な所」です。
垂直変波の波を出そうと思ったらヘンテナは1-3図に示すように横に寝かさなくてはなりません。
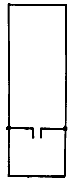 |
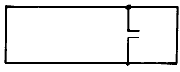 |
|
|
|
「第2の変な所」は、その長さが少しぐらいいい加減でも良く働く事です。
普通、アンテナの長さは L=1/2λ×0.98
等という計算式で算出されますが、実際に作って調整をしてみると、かなりシビヤな再調整が要求されるものです。
しかしヘンテナの場合は、ものさしが無くても慣れてくれば目分量で作ることが出来ます。
この性質は、全長2/3λまで引き伸ばすことが出来て、2/3λヘンテナとなります。
「第3の変な所」は、長さだけでなく、その幅も適当でなんとかなるものです。 厳密にいえば、エレメントの幅が狭いほど給電インピーダン
スは低いのですが、そのラチチュードは結構広いのです。 事実、この寸法のままで75Ωのケーブルを使ってもなんとか給電することができます。
「第4の変な所」はSWRの調整法です。
1-2図の所でお話したようにSWRの調整は給電点を上下に動かすだけです。 エレメントの基本的な大きさをいじる必要はまったくありません。
これは実際に調整してみると良く分かるのですが、実に便利な「変な所」です。
「第5 の変な所」は、これは重大なところですが、こんな簡単な構造のアンテナでありながら、大体4エレメントの八木宇田アンテナに匹敵
するゲインを持っていると言う事です。
変な所はまだまだあります。
鋏をもってきて1-4図のように上下のちょうど半分の所で二つに切り離してみてください。
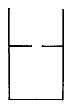 |
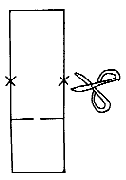 |
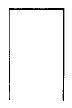 |
| こちらはフォークヘンテナ | 1-4図 長さ1/4λのところで切る |
こちらはただの針金 |
とかげのしっぽ切りではありませんが給電点のある方は立派にアンテナとして働いています。
これが「第6の変な所」です。 今度は1-5図のように横にしてから丸めてみましょう。 この場合発射される電波の偏波面は垂直偏波に変
わりますが、これでも立派なヘンテナです。(ハットヘンテナ)
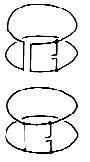 |
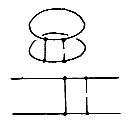 |
|
|
1-6図 丸めたヘンテナを再 び切り離す |
さぁ、段々難しくなりますよ。1-6図を見て下さい。ハットヘンテナを作るとき接合した場所の反対側×印のある所で切り開いてみましょう。 これ
でもちゃんと働いているのです。(Hヘンテナ) しかも、真ん中のショートバーのようなものを取り外してしまってもなおアンテナとして働いているのです。
長い間ヘンテナと付き合っているとこれらの事についてもそれ程変だとは思わなくなってきましたが、初めのうちは「変だなぁ」「変だなぁ」の連続でした。
それでは、私たちがどんな具合にヘンテナと付き合う羽目になったかというお話をすることにしましょう。
もう、23年も前の話になります(2001年起算)。
1972年7月、私が所属していた相模クラブ(現在再免許申請中)のミーティングの会場に当時最年少であったJE1DEU染谷さんから次のような提案が
ありました。
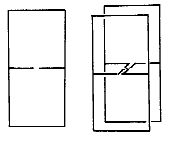 |
| 1-7図a 1-7図b |
「 1-7図aに示すようにクワッドを二つつないだエレメントを同図b
のようにHB9CV式の移相給電したらゲインが高く、FB比の良いアンテナができるのではないか」と、いうものでした。(この段階ではヘンテナという概念
は全く無かった)
彼が持ち込んだアンテナの模型を手にしているうちにクラブ員一同は催眠術に掛かったかのように「このアンテナをクラブとして開発しよう」と決定してし
まったのです。
さあ大変です。クラブ員の中に誰一人として「アンテナの測定法」を知っている人がいなかったのですから…。
本題に入る前に、その時のメンバーを紹介しておきましょう。
JE1DEU染谷さん ヘンテナを開発するきつかけを作ってくれました。 彼の提案はその段階ではうまく機能してくれませんでしたが、そ
の後もアルバイトで得た資金を全部参考書に注ぎ込んでアンテナについて研究を重ね、私達中古会員の尻を叩いてくれた「エキサイタ」です。
JR1SOP高橋さん 当時、送信機の設計のプロであった彼もアンテナでは一人のアマチュアでした。 この人のお陰でその頃まだ高峰の花
であった430MHzで実験ができました。また、ハットヘンテナの発案者です。
JA1TUT宇田川さん 通称トーチャン。クラブの会長です。
自ら第1号機を上げて日夜「へんなんですよ」「どうして飛ぶんでしょうねー」「本当におかしいですよ」がキャッチコピーでした。
JH1ECW阿部さん 当時、お父さんが農業をなされており、都会にあっては貴重な実験場の提供者です。(現在はテニスコート、老人介護
施設のお仕事をなさっています。)
測定、写真、整理等で骨を折って下さいました。
JH1XUQ新鍋さん 測定と解析を担当して下さいました。
JH1HPH宍道さん 団地の屋上に第2号機を上げました。 そのヘンテナの上にテレビのアンテナを乗せて、アマチュア無線のアンテナを
カムフラージしていました。
(1-8図) 大山、菜の花台で行った移動実験のチーフを担当して下さいました。
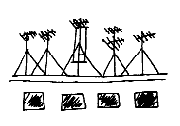 |
| 1-8図 団地の屋上でTVアンテナに カムフラージュしたヘンテナ |
JA1RKK中山さん 「ヘンテナ」の名付け親。 学校を出て、就職のため、クラブには顔を出していませんでしたが、会報を通じて
ヘンテナと関わりを持っていました。
JH1FCZ大久保 アンテナの実験の好きな私は、いつしかヘンテナのとりことなり、クラブとしての活動が無くなってからも、寝ながら
「ヘンテナ」「ヘンテナ」とウワゴトをいっていたようです。
こうして世の中に誕生したヘンテナは、その後、私が発行していたミニコミ誌、The Fancy Crazy
Zippy誌上に公表され、広がりを始めました。
そして、全国の皆さんからのリアクションによって増殖をはじめたのです。
このアマチュア無線家の連帯によってアメリカ、韓国、オーストラリアのアマチュア無線連盟の機関誌で発表され、最近ではアメリカのアマチュア無線連盟発
行の「The
ARRL antenna COMPENDIUM
Vol.5」にJF6DEA木下さんが紹介さたり、アンテナ設計のコンピュータソフト「MN」にもヘンテナが登場するようになりました。
このようにヘンテナは、純粋にアマチュア無線家の連帯によって開発された誇りあるアンテナなのです。
まずはヘンテナの基本型です。いろいろと後から面白そうなヘンテナが登場してきますが、初めからバリエーションに手を出すと、もともと「変テナ」
ですから訳が分からなくなってしまう可能性があります。 まずは、基本型ヘンテナでヘンテナの基礎を身に付けていただきたいと思います。
まず、2-1図に示すように、幅1/6λ、長さ1/2λのループを作ります。
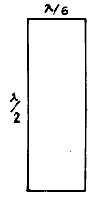 |
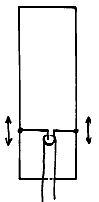 |
|
|
|
この材質は銅線、アルミパイプなど導体であればなんでも結構です。
これに同軸ケーブルの先を二つに分けた給電線を接続します
ヘンテナは「平衡型アンテナ」ですから、できれば同軸ケーブルの先にバランを付けてください。 SWRの調整は、給電点の位置を2-2図に示すように
ループに対してずらすことによって行います。 只作るだけだったら説明はこれだけです。 これ以上難しく考えると本当に訳が分からなくなってしまいそうで
すから、ここまでの説明を信じて一つ作ってみることにしましょう。
周波数は430MHz帯とします。
ループの幅は1/6λだと先ほど書きました。
さて問題は「λ」(ラムダと読みます)です。 λは「波長」を意味する記号で、アンテナの話の中にはこれからもたびたび顔を出しますから良く覚えておい
てください。
このλは次の数式(1)で計算することができます。
λ(m)=300/F(MHz)……(1)
今、仮に設計周波数を435MHzとすると…
λ=300/435=0.689655(m)
となります。 四捨五入して大体69cmですね。
この数字を6と2で割りますと、
λ/6=11.5(cm)
λ/2=34.5(cm)
となります。
つまり、幅11.5cm, 長さ34.5cmのループをまず作れば良いことになります。
このループの構造は針金で作ってもよいし、アルミのパイプで作っても良いのです。また、一部をパイプで作り、残る部分を針金で作っても良いので
す。
ループの固定の仕方は2-3図に示すように1/6λの半分の位置にポールが来るようにします。この場合、ポールの材質は金属でも、竹、木、グラスファイ
バー等なんでも結構です。
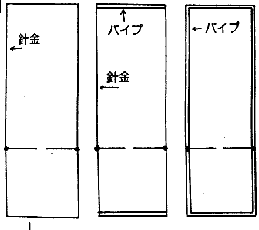 |
|
|
ヘンテナは、2-4図の構造で水平偏波の電波を発射することができます。
これを垂直偏波のアンテナとするには2-5図に示すように90°ずらしてやらなければなりませんがその場合、金属のポールで2-6図のように固定しては
いけません。必ず2-5図の方法で固定してください。
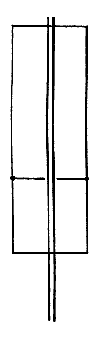 |
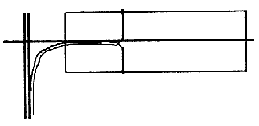 |
|
|
|
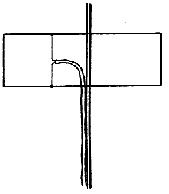 |
|
|
|
|
ただし、ポールの材質が絶縁物である場合はこの限りではありません。 この場合でも同軸ケーブルの引き出し方は2-6のようにしてはいけません。
必ず2-5図の方法で引き出してください。
バランは使用する周波数が430MHzと高いので、フェライトコアを使った強制バランは使えません。簡単なのは同軸ケーブルを利用したシュペルトップ
(バズーカマッチ)が良いと思います。
その構造は2-7図に示すような物です。
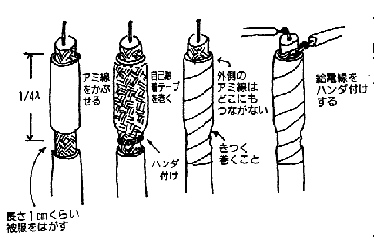 |
|
|
同軸ケーブルの外側に被せる編み線の長さは電気的に1/4λです。正確にはディップメータ等を使って測定しなければいけないのですが、計算上の1/4λ
で実際にはそれ程大きな問題は起きないようです。
編み線の上には自己融着テープをきつく巻き付けて置いてください。こうすることによって誘電体としての条件を一定に保つことと、雨水の浸透を防ぐことが
できます。
SWRの調整は給電位置をスライドすることによって行います。
SWRの値が1.2程度以下に下がっていれば、それ以上無理して調整する必要はありません。
どうしても1.5以下にならないときは給電線の長さが両方合わせて1/6λ以上になっていないか確かめてください。(2-8図)
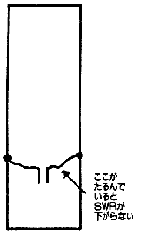 |
| 2-8図 SWRが下がらないとき |
この部分が長いとSWRがきれいに落ちてくれません。 ヘンテナを作るに当たって唯一気をつけなければならない箇所です。
430MHz帯では大多数の人が垂直偏波を使用しています。
ヘンテナを垂直偏波で使用するためには先程ものべましたように横長の形に設置する必要があります。
アパートやマンションにお住いの方は2-9図のようにベランダから横方向にポールを突き出して使うことができます。
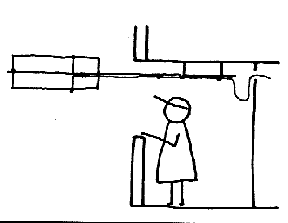 |
|
|
430MHz帯は広い周波数帯を持っていますが、都会地においてはそれでも空いているチャンネルを探すのは大変な仕事です。
そんな場合、ローカルの仲間同志で水平偏波のヘンテナを作って運用して見ると、「430MHz帯はこんなに空いていたか」と認識を新たにすることができ
ると思います。
ヘンテナは430MHzだけでなく他の周波数の物も同じように簡単に作ることができます。
エレメントの長さの計算はまず作りたい周波数のλを計算して、その値を6と2で割り、幅と長さとします。
例えば7MHzの場合は
λ=300/7.050=42.55
λ/2=42.55/6 =7.09
λ/6=42.55/2 =21.27
となります。 これはちょっと大きいですね。でも、都合の良い周波数でヘンテナを実際に作ってみることによって「あなたのアンテナに関する常識」 は、かなり大幅に塗り替えられてしまうのではないかと思います。
ここでもう一段ヘンテナのにん関する知識を深めていただきましょう。
ヘンテナは2-10図に示すように二つのループに分けて見ることができます。
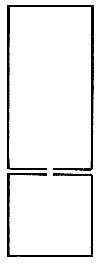 |
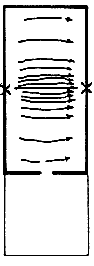 |
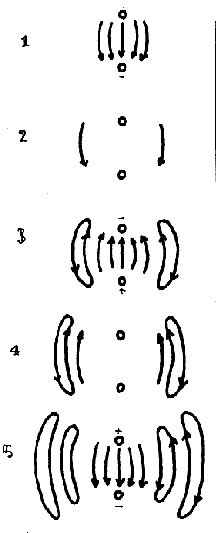 |
| 2-10図 ループが 2つ | 2-11図 ヘンテナの中の電気力線 | 2-12図 ヘンテナから電波が飛び出す (水平偏波ヘンテナを上から見る) |
上側の大きなループでは、ループの中央部に電圧の腹部が来ます。 その結果、この部分に「電気力線」が2-11図のように発生します。 この電気
力線の方向は周波数の1/2サイクル毎に180°方向を変え、電波となって空間にとびたっていきます。(2-12図)
そしてこの電気力線の方向が偏波の方向を示しているのです。
もしこの電気力線の方向に金属等の導電性のある物体を置いたとすると、電気力線は2-13図に示すようにその導体の中に吸収されてしまいます。
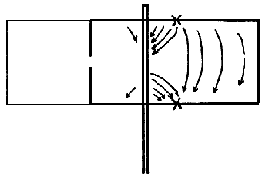 |
|
|
その空間に電気力線が無くなると言う事は取りも直さず電波が発生しないということになります。
これで垂直偏波にした場合エレメントの中央部に金属ポールを持ってきてはいけない理由がお分かりいただけたことと思います。
小さい方のループにも小さいなりの電気力線が発生します。そしてこの電気力線の向いている方向は、大きなループで発生している電気力線と同じ方向
を向いていますから、アンテナのゲインとしては若干増強する形になります。
ゲインの増強がそれ程大きなものでないのなら、この小さいループの存在意義が無くなりそうですが、それがそうでないどころか大きな意義を持っているので
す。
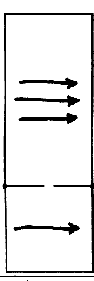 |
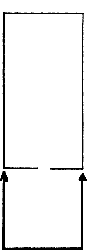 |
| 2-14図 下のループにも同 相の電気力線が… | 2-15図 下のループはマッチ ングセクションとしても働く |
次はループの幅です。
簡単に「1/6λ」と言ってきましたが、この幅が狭くなると給電インピーダンスが低くなり、逆にこの幅が広くなると給電インピーダンスは高くなります。
(2-17図) 給電インピーダンスの高低つまり、ループの幅の広い、狭いは、ゲインに関してそれ程大きな影響は与えませんが、ループ幅の広いほどSWR
の低い周波数範囲が広く(周波数帯域が広く)なります。
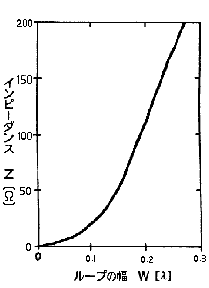 |
|
|
以上のことが分かってくれば、ヘンテナのいろいろなバリエーションを何の問題もなく自由自在に製作できるようになると思います。
| ・戻 る | ホーム | 進む・ |